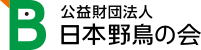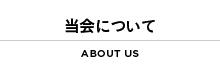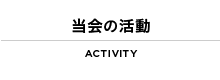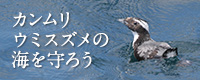- 日本野鳥の会
- 当会の活動
- 自然保護
- 絶滅危惧種の保護
- シマフクロウ保護の取り組み
- シマフクロウとの共存ルールについて
- シマフクロウとの共存ルール
シマフクロウとの共存ルール
シマフクロウは絶滅危惧種であり、国の保護対象種です。生息環境の悪化により、20世紀後半には絶滅寸前まで個体数が減少しました。しかし、環境省や保護関係者、関係機関による数十年にわたる地道な保護活動により、生息数はじょじょに回復しています。
しかし、まだ絶滅の危機を完全に脱したわけではなく、生息環境の保全や再生に向けた取り組みを継続することが必要です。また、野生のシマフクロウの観察を積極的に推奨できる状況ではありません。
近年、シマフクロウの繁殖地付近でのむやみな接近や立ち入りによって、採餌や繁殖が妨害される事例が確認されています。人間の行動による生息環境の悪化を防ぐため、次のルールを守ってください。
おどかさないよう、そっと離れてください
シマフクロウを見つけたときは
- 大声を出したり、近づいたりせず、生活をさまたげないようにしましょう。
- 長時間の観察は避け、そっと離れてください。
- 「逃げないから大丈夫」ではありません。 人がいる間はずっと警戒し、緊張している可能性があります。
観察や撮影はシマフクロウにストレスを与える可能性があります。
光をあてないでください
撮影時の注意点
- フラッシュを使った撮影は禁止です。
- サーチライトや懐中電灯などで照らさないでください。
夜行性のシマフクロウに強い光を当てると、視力に悪影響をおよぼし、ストレスの原因になります。
巣やヒナ、幼鳥には近づかないでください
繁殖をさまたげないために
- 巣を探したり、巣のある木の周辺に近づいたりしない。
- ヒナや幼鳥に近づいて写真を撮らない。
- 人間が近づくと親鳥が警戒し、営巣・産卵・抱卵・育雛を放棄する可能性があります。
- 天敵(キタキツネ・エゾクロテン)を誘引する原因になることがあります。
シマフクロウの繁殖成功率は低く、1回の繁殖が極めて重要です。
もし偶然、巣やヒナを見つけた場合
- すぐにその場から離れてください。
目撃地点の情報や巣の場所を拡散しないでください
SNSやブログ投稿の注意点
- 巣や幼鳥の写真を公開しない。
- 「この森でシマフクロウを見た!」といった生息情報を発信しない。
- 位置情報のついた写真を投稿しない。
生息情報が拡散されると、観察者やカメラマンが押し寄せ、シマフクロウの繁殖や採餌をさまたげる恐れがあります。
餌付けしないでください
餌付けのリスク
- 野生本来の生態が乱れ、自力で餌を取る能力が低下します。
- 天敵(キタキツネ・エゾクロテン)を誘引し、シマフクロウが襲われる危険性があります。
- 人慣れすると事故に遭いやすくなります。
一部の観光事業者による餌付けは、環境省が認めたものではありません。
保護増殖事業における給餌は、科学的根拠に基づき、必要最小限の範囲で行われています。
巣箱を設置しないでください
勝手な巣箱設置のリスク
- 天敵による捕食を招く可能性があります。
- シマフクロウの生息環境に悪影響を与える恐れがあります。
環境省の保護増殖事業では、専門家の監修のもと、計画的に巣箱の設置・管理を行っています。
シマフクロウの未来を守るために
環境省や関係者は、これらのルールを守りながら生息状況調査や環境保全に取り組んでいます。
皆さまのご理解とご協力が、シマフクロウの安心できる未来につながります。
もしルール違反を見聞きした場合
環境省までお知らせください。
- 環境省北海道地方環境事務所
TEL:011-299-1954 - 環境省釧路自然環境事務所
TEL:0154-32-7500
立入禁止区域や私有地への無断立ち入りは絶対にやめてください。
職員・監視員へのご協力をお願いします
国立公園、鳥獣保護区、国有林では、環境省や林野庁の職員、委嘱を受けた監視員が巡視を行っています。
現地で指示を受けた場合は、必ず従ってください。
シマフクロウが見られる動物園
現在、保護増殖事業の一環として、いくつかの動物園でシマフクロウが飼育されています。
繁殖が成功した場合、ヒナを見ることもできます。
シマフクロウを観察したい方は、ぜひ動物園へ足を運んでください。
- シマフクロウがいる動物園(環境省ホームページ)
まとめ
シマフクロウと共存するために、次のことを守りましょう!
- むやみに近づかない・観察しすぎない
- 光を当てない
- 巣やヒナには絶対に近づかない
- 生息地の情報を拡散しない
- 餌付けをしない
- 勝手に巣箱を設置しない
シマフクロウの未来を守るため、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
出典:「シマフクロウとの共存ルール」(環境省ホームページ)を加工して作成